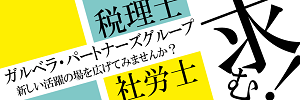ガルベラグループの
人事評価制度構築サポート
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
|---|
大阪事務所 | 大阪府大阪市西区立売掘1-2-12 本町平成ビル3階 |
|---|
福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
|---|
名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
|---|
このようなお悩みはありませんか?
- 役職に見合うだけの働きをしていない社員がいる
- 新人が入社した後のキャリアパスを示したい
- 職責の自覚をもった社員を増やしていきたい
- もっと管理職に成長してもらいたいと思っている
職能資格等級
職務遂行能力(略して、職能)を中心に等級を設計していく制度。能力が上がれば、上位の資格に相当し、それに比例して等級も上がっていくという考え方に基づいています。組織での在籍年数が長くなれば組織内での能力が上がっているとみなされることが多いので、在籍年数に応じて等級が上がりやすく、日本社会で培われてきた「年功序列」や「終身雇用」となじみやすいのが特徴。人材を雇用してから、部署異動や転勤などを経て、キャリアアップしていくことを可能にしています。そのため、企業への帰属意識が高まり、人材の長期確保へと繋がっていきます。一方で、年功序列のイメージで捉えられることが多く、改革が必要だと近年言われることも多くなっています。

メリット
- 人事異動させやすい
- 役職等に空きがなくても不満につながりにくい
- 長期的な人材確保につながる
デメリット
- 長期的には人件費が高騰する
- 年功序列のイメージが強く若手がモチベーション低下を招くことがある
- 何を評価しているのかが不明瞭だと捉えられてしまう
職務等級制度
職務(仕事内容)やそのレベルの仕事に合わせて等級を設計していく制度。人に紐づいた(属人的な)能力を基準とするのではなくて、職務の内容を基準に評価し等級区分していきます。昨今よく話題になる「ジョブ型」は職務等級制度で運用していきます。欧米では主流と言われることも多い制度で、給与と仕事内容が紐づいているので、実力主義の人にはモチベーションアップにつながることも。スペシャリストの育成につながりやすい制度です。

メリット
- 給与と賃金がマッチし合理的
- 職務内容が明確になる
- 人件費の変動が起きにくい
デメリット
- 職務が変わらなければ賃金があがらない
- 人事異動させるのが困難
- 組織・職務が硬直化しやすい
役割等級制度
会社から与えられた役割の大きさや、担うべき役割の重要度等により等級区分する制度。企業が求める役割を社員一人一人に設定し、その成果に応じて等級を区別や序列化する仕組みとなります。役割を具体的に目標に展開し、その達成度等を処遇に反映させることで、社員の自主性や自律性を引き出すことを目的とします。
期待される役割が明確になり、バランスのとれた合理的な評価が可能で、組織改編など柔軟性のある対応ができます。一方で、役割が変更した場合に再定義が必要というデメリットもあるでしょう。

メリット
- 役割意識を持たせやすい。とるべき言動に紐づけやすい
- 役割評価が比較的分かりやすい
- 総人件費が高くなりすぎない
デメリット
- 説明をするのに説明能力が必要になる
- 役割が変更した際に、役割定義をしなおす必要がある
- 役割の拡大を希望しない社員には不利になる可能性がある
3つの等級制度
| 職能資格制度 | 職務等級制度 | 役割等級制度 | |
|---|---|---|---|
| 基軸 | 能力(能力基準) | 職務(職務基準・仕事基準) | 役割(役割基準) |
| 主な メリット | ①人事異動させやすい ②役職等に空きがなくても不満につながりにくい ③長期的な人材確保につながる | ①給与と賃金がマッチし合理的 ②職務内容が明確になる ③人件費の変動が起きにくい | ①役割意識を持たせやすい。とるべき言動に紐づけやすい ②役割評価が比較的分かりやすい ③総人件費が高くなりすぎない |
| 主な デメリット | ①長期的には人件費が高騰する ②年功序列のイメージが強く若手がモチベーション低下を招くことがある ③何を評価しているのかが不明瞭だと捉えられてしまう | ①職務が変わらなければ賃金があがらない ②人事異動させるのが困難 ③組織・職務が硬直化しやすい | ①説明をするのに説明能力が必要になる ②役割が変更した際に、役割定義をしなおす必要がある ③役割の拡大を希望しない社員には不利になる可能性がある |
ご覧いただいてわかる通り、それぞれに一長一短がございます。弊社はそれぞれの特徴を踏まえ、貴社に最適な等級制度を構築するお手伝いをさせていただきます。自社にあった等級制度を設定したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
昇格・降格の考え方

昇格の基準こそ等級制度の要諦
「昇格」は等級制度において等級が上がること、「降格」は等級が下がることをいいます。一方、「昇進」は高い役職に就くこと、「降職」は低い役職に就くこと、の意味で表現されるケースが多いです。
日本企業でよく見られる職能資格制度では、通常、能力が伸長し、現等級の能力が十分に身に付き、上位等級の能力を満たす可能性がある場合に昇格します。
厳密な表現ではありませんが、一般的によく用いられることの多い、職能資格制度における昇格基準である「卒業方式」・「入学方式」の考え方にも触れておきましょう。
・卒業方式…現等級の能力を十分に満たしたことを要件として昇格させること。現等級で規定される職務遂行能力を身につけ等級の基準を満たした、つまりその等級を「卒業」して、次の等級に進んでよい、という考え方。
・入学方式…上位の等級で求められる能力を満たす可能性があれば昇格させる、という考え方。現等級で求められる能力を満たすのは当然であり、上位の等級で求められる能力を身につけなければ「入学」はできない(昇格はできない)ことになります。
「卒業方式」「入学方式」どちらの方式でも間違いではありません。自社での昇格の考え方に基づき昇格ルールを設定していく必要があります。
昇格・降格を運用していくうえでの留意点
昇格を運用するうえで、以下のポイントが重要になります。透明性のある人事評価制度を目指すのであれば、外せない点となります。
- 昇格基準の設定
- 昇格の手順の明確化
- 昇格者の発表
次の等級に進むためには、どういった能力を身に着ければよいのか(職能資格制度)、どういった職務を遂行するのか(職務等級制度)、どのような役割を果たせばよいのか(役割等級制度)、従業員がわかりやすく基準を設定しておく必要があります。
昇格対象者の決め方、上司による昇格の推薦方法、最終決定(承認)の方法などを予め決めておき、手順に則って昇格が運用できるように進めていきます。
同様に、降格の場合も手順を決めておく必要があります。降格はモチベーションダウンにつながる恐れもありますので、より慎重な運用が求められます。具体的な手順の設定方法や運用上の留意点が気になる方は、ぜひお気軽に弊社までお問合せください。
電話でのお問合せ
お問合せは、お電話・メールにて
受け付けております。
【東京事務所】
【大阪事務所】
【福岡事務所】
メールでのお問合せは
24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
税務・労務・法務・海外進出などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。
ガルベラ・パートナーズグループで共に働く仲間を探しています。
アプリ開発やシステム開発
IT業界のサポートが可能